






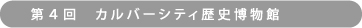



第3回 ミイラ猫の博物館
3−1 あのあと、吉沢さん(仮名)の話は2時間にもおよんだ。
あのあと、吉沢さん(仮名)の話は2時間にもおよんだ。
弟が失踪した日の朝から始まり、そのあと4年間、自分がなにをし、なにをしなかったのか。誰と出会って、誰と出会わなかったのか。見つけられた手がかりと見つけられなかった手がかり。目撃者の証言、警察の判断、何千枚と刷られた捜索願い、謎と徒労と失望、エトセトラ。話は途中大きく迂回し、そこからさらに枝分かれし、本筋を失いそうになる手前で、またもとの道に戻ってくる。それを何度か繰り返した。彼女の中には、確固とした明瞭な一本の筋が見えている。聞き手である僕はときたま相槌を打つだけだ。それは自分のために打っていた。そうしないと、相変わらず彼女は空に向かって喋るだけで、僕が心細くなってしまうのだ。僕は自分の存在を確認するために、うん、とか、ああ、とか呟いた。
おそらく彼女は、何度もこの話をしているのだろう。もしかしたらこの博物館にやってくる客を、手当たり次第に捕まえては話しかけてるのかもしれない。まるで戦争被害者が観光客相手に語り伝える悲劇の証言のように。つまりそれはよくできていた。本当に台本があるんじゃないかとさえ思った。そこにはシリアスな絶望とシニカルな視線が同居していた。訴えるに十分なテーマもあったし、プロットはミステリー小説なみに機知に富んでいた。しかしその完成度の高さ故に僕は違和感を感じたのだ。あくまでも彼女は当事者であり、残された被害者なのだ。もっと声を詰まらせ、露骨に感情を出してもいいのではないか。あまりにも明瞭な語り口が僕を鼻白ませた。ひいては、こういう種類の話を見ず知らずの人間にするってどうなのよ、と思った。でも同時に、僕には身内が行方不明になった体験がないからその心痛が理解できないだけなのかもしれない、とも思った。
結局のところ、僕が気に食わなかったのは、吉沢さんの独白の相手は、僕じゃなくてもいいってことだ。吉沢さんの中で、ただ事件を風化させたくないという思いがあって、この悲劇は誰かに伝えなければいけないという使命のもと、そこにのこのこ現れたのが僕だった、というわけだ。僕は選ばれたわけではない。途中から話半分で聴いた。心のどこかに戦艦大和の沈没を見つめるおじいちゃんと重ねていた。
ああなんという心の狭さよ、おれ。
元来、僕は深刻な話題に弱い。まじめな空気が流れると、すぐにあくびをしたくなる。葬式とか大の苦手だ。坊さんの頭をじっと注視して、徐々に坊さんの頭が違うものに見えてくるのを楽しんだりしてしまう。僕に相談話を持ちかける人は、だいたいがっかりして帰っていく。その話題がシリアスであればあるほど、僕はその場からふわふわと浮いていってしまう。「もっと自分のことだと思って聞きなさい!」と母親にはよく怒られた。実際に自分のことで怒られてるにも関わらずだ。ちょっとした解離性障害なのかもしれないが、精神病院に行っても真面目に先生の話は聞けないと思うから止めている。
吉沢さんの話はそういう意味でも僕には荷が重い。
マジやんか、とつっこみたくなる。またまた冗談でしょ、とお茶を濁して、じゃ映画でも見に行こうか、と言いたい。しかし言えるわけがない。
彼女の2時間の語りを要約すれば、わずか3行でまとめられる。
私の弟が消えた。
しかし、彼は必ずどこかでまだ生きている。
私には、それがわかる。
あれ、インディアンの話はなんだっけ。そうだ確か、弟は失踪前日にインディアンの本を読んでいたのだ。で、この博物館の門前にはインディアンの絵が書かれていた。それはエドモント・テーラー家の歴史に深く関わってくる人々だ。
確かに僕は帰り際にその絵を確認したが、よくこんな小さなものを弟はめざとく見つけたもんだと感心した。
「弟はきっとこの家に、インディアンが住んでいると思ったのでしょう。そして会って話を訊きたかったんだと思います」
「どんな話を?」
「本当に、人間の頭の皮を剥ぐのかどうかを」

